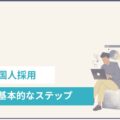外国人労働者を受け入れる企業が年々増加する中、雇用現場では言語や文化の違いだけでなく、在留資格や契約書の整備、労働条件の理解不足など、法的なトラブルが後を絶ちません。現場の対応だけでは解決が難しい問題が、企業の評判や人権問題にまで波及することもあり、リスクは想像以上に広がっています。
「外国人雇用を始めたが、在留資格の確認に不安がある」「制度が複雑すぎて、何が正しいか分からない」そんな悩みを抱えていませんか。特に労務管理の不備や契約書の不備は、トラブル発生時に企業側が不利な立場に立たされる原因となり得ます。場合によっては、不法就労助長罪などの刑事リスクにまで発展することもあるのです。
日本では、外国人の雇用に関する制度や入管法の整備が進んでいますが、企業側がそれらを正確に理解し、実務へ落とし込むことは容易ではありません。だからこそ、法律事務所による法的支援や弁護士との連携体制の確立が、外国人雇用を成功させる鍵となるのです。
トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼を守るには何が必要か。その答えは、正しい知識と的確な対応、そして法律のプロによる実務的なサポートにあります。最後まで読むことで、契約から就労、解雇まで、外国人雇用の現場で起こり得るリスクとその対応策を、明確に把握できるようになります。損失を未然に回避し、安心して外国人労働者と向き合うための第一歩を、今ここから始めてみませんか。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

| みなとワークス | |
|---|---|
| 住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
| 電話 | 052-387-9955 |
外国人雇用に弁護士が必要とされる理由とは?
外国人労働者の雇用における法律的リスク
企業が外国人労働者を雇用する際には、想像以上に多くの法的リスクが潜んでいます。日本の法律、特に入管法や労働基準法に関する知識が不十分なまま採用を進めると、知らず知らずのうちに違法状態に陥る可能性があります。
以下の表に、日本で外国人を雇用する際に発生しやすいリスクの具体例を整理しました。
| 主なリスク | 内容 | 想定されるトラブル事例 |
| 在留資格外活動 | 許可されていない職種での勤務 | 技能実習生をコンビニで就労させたことによる摘発 |
| 不法就労助長罪 | 就労資格のない外国人を故意または過失で雇用 | 在留カードの有効期限切れに気づかず継続雇用し罰則 |
| 労働条件の不備 | 労働契約書の不在・内容不明確 | 残業代未払いや休日出勤の訴訟 |
| 差別的扱い | 日本人と異なる処遇(昇給・福利厚生) | 労働審判に発展した事例もある |
| 社内体制の不備 | 外国人特有の対応フローが未整備 | 苦情対応の遅れによる不信感と退職者の増加 |
これらのリスクは、外国人労働者の増加とともに全国の企業にとって身近な問題となっています。特に中小企業では、人的・法的なサポート体制が整っておらず、リスクを見過ごしやすい傾向があります。
日本語や制度への理解が不十分な外国人労働者に対して、不本意なトラブルが起きた場合、会社側が「説明したつもり」であっても、それが認められないという裁判例も存在します。労務・入管の両面での専門知識が問われるこの領域では、単なる書類上の整備だけではリスクヘッジにならないのです。
企業が法的リスクを未然に防ぐためには、制度を正しく理解することはもちろん、日々変化する制度・法律への対応力も求められます。信頼できる法的パートナーと連携し、継続的な法務体制の構築が今後の企業経営において不可欠です。
弁護士が果たす役割と企業への支援内容
弁護士が果たす外国人雇用の分野での役割は多岐にわたり、単なるトラブル対応にとどまりません。むしろ、トラブルを未然に防ぎ、企業が安定して外国人労働者を雇用・活用できる環境づくりをサポートする「法務パートナー」としての側面が強くなっています。
まず弁護士は、採用時の契約書作成や就業規則の見直しを支援します。特に外国人労働者向けの契約書には、在留資格との整合性、就労可能な業務範囲の明記、言語対応(英語・中国語など)といった配慮が必要です。これを怠ると、のちの労使トラブルや入管からの指摘につながるため、法的知識のある専門家による整備が欠かせません。
在留資格申請時のアドバイスや行政機関との調整も重要な支援内容です。入管への対応は、一般的に行政書士が行うことが多いですが、法律解釈や複雑な事例では弁護士が直接サポートに入ることもあり、より高度な判断が必要となる場面で力を発揮します。
弁護士は外国人従業員と企業とのトラブル発生時における法的代理人としても機能します。たとえば、労働紛争や不当解雇の申し立てに対して、弁護士が交渉や訴訟対応を担うことで、企業の法的リスクを最小限に抑えることができます。
以下は、企業が弁護士に依頼できる主な支援業務の一例です。
| 支援内容 | 詳細項目 |
| 契約書作成・整備 | 雇用契約書の多言語対応、特約条項の設計 |
| 労務管理アドバイス | 残業・休日・解雇時の対応方法、差別的処遇の防止策 |
| 在留資格に関する支援 | 就労資格確認、更新・変更申請に伴うリスク分析 |
| 入管対応 | 書類作成の法的監修、申請時の戦略アドバイス |
| 労働トラブル対応 | 訴訟・調停・審判への代理出席、事前交渉・和解の提案 |
| 顧問契約に基づく継続的支援 | 法改正への即応体制、社内研修や講演の実施 |
外国人雇用に対応する弁護士の多くは、国際労働問題や入管法の専門性を高めており、特定技能制度や技能実習制度などの制度にも明るい知識を持っています。弁護士がいることで、採用計画から在留資格取得、就業後の労務管理まで、全体を俯瞰しながら最適なサポートを受けられる点が最大の魅力です。
企業にとっては、単発の相談ではなく顧問契約として継続的に法務リスクに備える体制を構築することが、今後ますます重要になります。外国人雇用を戦略的に進める企業ほど、弁護士との連携がビジネス成長に直結する時代です。
他の専門家(行政書士・社労士)との違い
外国人雇用を巡る法務支援においては、弁護士以外にも行政書士や社会保険労務士(社労士)といった専門家の存在が知られています。これらの資格者と弁護士の違いを正しく理解し、適切に役割分担を行うことが、企業にとって重要です。
行政書士は、主に在留資格の取得・変更・更新といった入管への書類作成および申請業務を行います。一方、弁護士は入管業務に加え、申請の不許可処分に対する異議申し立てや訴訟対応が可能です。つまり、行政書士が対応できるのは「書類の手続き」に限られ、法律的な争いに関わる業務には関与できません。
社労士は労働社会保険の手続きや労務コンサルティングを担う専門家であり、外国人労働者の社会保険加入や給与計算、労使協定の整備などを得意とします。ただし、法的トラブルや裁判への対応は弁護士の専権業務であり、社労士では対応できません。
下記は、それぞれの専門家の業務範囲を比較した一覧です。
| 資格者 | 主な業務範囲 | 法的対応・代理権 |
| 弁護士 | 労働紛争、契約書作成、訴訟対応、入管異議申立てなど | 裁判・交渉すべて可 |
| 行政書士 | 在留資格の書類作成と申請、ビザ更新サポートなど | 書類作成・提出のみ対応 |
| 社会保険労務士 | 労働保険・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算など | 調停・訴訟などは非対応 |
在留資格・就労ビザに関する基礎知識と弁護士のサポート内容
在留資格の種類と就労可能な範囲の違い
外国人が日本で合法的に働くためには「在留資格」が必要です。在留資格とは、日本に滞在する理由や目的を法律上定めたもので、就労の可否や可能な職種などが細かく区分されています。現在、日本に存在する在留資格は30種類以上に及び、そのうち就労が認められているのは一部のみです。
とくに企業が注目すべきは、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、就労可能な資格の範囲です。それぞれの在留資格によって、外国人が従事できる業務の内容や雇用条件が異なるため、採用前にその資格の要件を正確に把握することが求められます。
これらの在留資格のうち、企業が採用を行う上で最も利用頻度が高いのが「技術・人文知識・国際業務」です。この資格は、外国人大学卒業者を専門職として正社員で雇用する際に多く活用されています。しかし、この資格で認められる業務範囲を逸脱した場合、企業と本人の双方が処罰対象になる恐れがあるため、就労内容と資格内容の整合性が極めて重要です。
「特定技能」資格は、技能実習制度の後継とも位置づけられる制度で、近年急増しています。特に介護・飲食・宿泊などの分野では、特定技能人材の導入が加速していますが、受け入れ企業には労務管理や支援体制の構築義務があり、実務面での準備が不可欠です。
外国人労働者の採用を検討する企業には、在留資格の選定から申請、維持管理までを一貫して対応できる体制が求められます。ここでは弁護士による専門的なアドバイスが大きな価値を持ちます。とくに法改正や制度変更に伴う要件の変更には迅速な対応が必要であり、弁護士と連携して最新情報を常にキャッチアップすることが、リスクを避けるうえで非常に重要です。
弁護士が行う在留資格申請・更新のサポート業務
企業が外国人を雇用する際には、在留資格の申請や更新の手続きが発生します。これらの手続きは、煩雑な書類の準備と高度な法的知識を要するため、弁護士によるサポートが極めて有効です。
在留資格の申請業務では、雇用契約書や職務内容の説明資料、会社案内、給与証明、納税証明など多岐にわたる書類を作成・提出する必要があります。これらは、単に揃えるだけでなく、申請の主旨に応じた法的整合性や内容の妥当性が審査されます。たとえば、職種が在留資格に適合しているか、報酬が日本人と同等であるか、事業の継続性が担保されているかなどが、判断のポイントとなります。
弁護士が行うサポート内容は以下の通りです。
| 弁護士による支援業務 | 内容説明 |
| 申請書類の監修および代理作成 | 入管法に準拠した正確な書類作成、誤記載や記載漏れの防止 |
| 雇用契約の法的チェック | 労働法・入管法に整合する内容かの確認 |
| 更新時の条件確認とリスク分析 | 更新不許可のリスク回避策、審査要件の再確認 |
| 不許可時の対応(異議申し立て・審査請求等) | 入国管理局に対する法的主張と補足資料の準備 |
| 企業内コンプライアンス指導 | 在留資格の維持に必要な社内管理体制の整備サポート |
特に注目すべきなのは、在留資格の更新において「中途退職」や「業務変更」があった場合のリスク対応です。在留資格は特定の活動内容に基づいて発給されるため、職種変更や待遇変更によっては更新が認められないケースがあります。その際、企業が事前に弁護士と連携し、対応策を講じることで、外国人社員の不利益や企業の雇用計画の破綻を防ぐことができます。
不許可になった場合の異議申し立てや再申請には、法的根拠を提示した明確な主張が求められます。弁護士であれば、法的観点からの理由付けとともに、説得力のある申立書類を作成し、行政対応の成功率を高めることができます。
外国人労働者を多く採用している企業では、定期的に弁護士と顧問契約を結び、入管対応のフローを平準化しておくことで、スムーズかつ法的リスクの少ない運用が可能となります。特に現在では、入管法や制度の改正が頻繁に行われており、最新の制度を反映した対応が求められています。
技能実習生・特定技能制度における法的サポート
技能実習制度や特定技能制度は、近年日本国内で急速に拡大している外国人労働力の受け入れスキームであり、それぞれ異なる法律構造と管理体制を有しています。企業がこれらの制度を活用する際には、弁護士による法的サポートが極めて重要です。
まず技能実習制度とは、開発途上国への技能移転を目的として創設された制度で、企業は管理団体を通じて実習生を受け入れる形を取ります。この制度はあくまで「技能習得」が目的であり、単純労働力の確保を目的とすることは法律上許されていません。そのため、受け入れ企業には実習計画の厳格な運用と適正な労働環境の整備が義務付けられています。
一方で、特定技能制度は深刻な人手不足を補う目的で創設され、一定の技能水準と日本語能力を満たした外国人が特定産業分野で就労できる制度です。受け入れ分野は14業種に限定されており、介護・外食・農業・建設などが代表例です。
弁護士が支援する具体的な業務は以下の通りです。
| 支援領域 | 内容 |
| 実習計画・支援計画の作成監修 | 法令に適合した実習・支援計画の策定、提出書類の監修 |
| 労務管理の整備 | 就労時間・休暇・住居提供などに関する労務体制のチェックと改善提案 |
| トラブル発生時の対応 | 実習生とのトラブル(暴力、パワハラ、賃金未払い)に対する法的対応 |
| 管理団体・登録支援機関との調整 | 指導強化の場面における企業の法的立場の明確化 |
| 行政監査・改善勧告対応 | 出入国在留管理庁や外国人技能実習機構からの指導に対する説明資料の作成と交渉対応 |
技能実習制度においては、制度の主旨に反した運用を行うと、監査対象となるだけでなく、最悪の場合は実習生の受け入れ停止処分を受ける可能性があります。特定技能制度でも、受け入れ企業が支援義務(生活支援・相談対応など)を怠った場合には、登録支援機関の交代や資格の取り消しといった厳しい措置が科されるケースもあります。
そのため、制度に精通した弁護士によるサポート体制があることで、制度違反を未然に防ぎ、安定した人材受け入れと定着を実現できます。現在、入管行政や労働環境への社会的関心も高まっている中で、企業の信頼性を高める手段としても、法的支援体制の構築は急務となっています。
不法就労を防ぐための実務対応とコンプライアンス整備
不法就労助長罪の罰則と企業が取るべき対策
外国人労働者を受け入れる企業にとって、不法就労助長罪は決して他人事ではありません。企業が無自覚のまま在留資格を逸脱した雇用を行った場合、たとえ「知らなかった」という理由でも法的責任を問われるケースが存在します。この問題は企業にとって重大な法的リスクであり、特にコンプライアンス体制の不備があると、刑事罰のみならず社会的信用の喪失に直結するのです。
不法就労助長罪とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に定められており、外国人に対して不法就労をさせたり、これをあっせんしたりする行為に対して処罰が科される法律です。この罪に該当すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が課されます。企業の代表者だけでなく、担当者や実務レベルの管理者も処罰対象となる可能性があり、非常に厳しい法規制です。
このリスクに対して、企業が講じるべき基本的な対策は主に以下の通りです。
不法就労防止のために企業が取るべき実務対策(例)
| 項目 | 対策内容 |
| 採用前確認 | 在留カード・資格外活動許可の有無を厳密にチェックする |
| 雇用契約書 | 雇用内容が在留資格に適合しているか専門家に確認する |
| 定期モニタリング | 在留資格の期限や変更を定期的に確認し記録管理する |
| 社内教育 | 採用担当者・管理職へ外国人雇用に関する研修を行う |
| 顧問弁護士連携 | 不明点がある場合は即時に弁護士へ確認し対応する |
ここで問題となるのは、「外国人労働者の在留資格は何を根拠に判断すればよいのか?」という疑問です。在留資格には約30種類あり、それぞれが就労可能な活動内容を厳格に定めています。「技術・人文知識・国際業務」資格を持つ外国人は、通訳・エンジニア・法務・会計など専門業務に限定して就労が可能です。一方で、単純労働に分類される工場作業や清掃業務などは原則として認められておらず、これに該当する雇用を行えば不法就労助長罪の対象となります。
よくある誤解として「本人が『働ける』と言っていた」「在留カードがあるから大丈夫だと思った」というケースがありますが、企業側が在留カードの記載内容を正確に理解せず、実態と合わない職務に就かせた場合は助長罪が成立し得ます。そのため、採用担当者は在留カードの内容を正しく読み取るスキルと、業務内容と資格との整合性を確認する体制が不可欠です。
弁護士との連携も極めて重要です。特に入管業務に精通した弁護士は、外国人雇用に関するリスク診断や就労範囲のアドバイス、行政との対応サポートまで行うことができます。最近では、在留資格確認のクラウドシステム導入や弁護士監修の就業規則マニュアルの整備など、より高度な対応が企業に求められるようになってきています。
不法就労助長罪のリスクを真に回避するためには、「知らなかった」では済まされない制度的理解と運用が不可欠です。行政処分や刑事罰による損失はもちろん、企業の社会的評価や外国人採用ブランドにも大きな影響を及ぼす可能性があるため、法令順守の姿勢を明確に打ち出すことが、今後の外国人雇用における競争力の源となるでしょう。
雇用前の在留カード・資格確認の実務ポイント
外国人を雇用する企業にとって、採用前の在留カード確認は、法的責任を回避するための第一歩です。在留カードに記載された情報を正確に理解し、就労可能な在留資格かどうかを判断することは、不法就労の防止とコンプライアンス対応の両面において非常に重要です。しかしながら、企業側の理解不足や制度の複雑さにより、不適切な採用が発生するリスクが未だに多くの企業で見受けられます。
在留カードの確認にあたっては、以下のような情報を詳細に精査する必要があります。
在留カード確認の必須チェック項目
| チェック項目 | 内容の確認ポイント |
| 在留資格 | 就労可能な在留資格か(例 技術・人文知識・国際業務、特定技能等) |
| 就労制限の有無 | 「就労制限なし」または「指定された活動に限る」かどうか |
| 在留期間 | 在留期限内かつ十分な残存期間があるか |
| カード真贋 | 偽造でないかを外観・ICチップ読み取り等で確認 |
| 発行元 | 地域入国管理局発行の正規なものかどうか |
企業がこの確認作業を怠った場合、後々になって本人の就労が不許可だったことが判明し、企業に対して行政指導や刑事処罰が下されるおそれがあります。特に外国人労働者の雇用が多い飲食業や介護、建設業界などでは、採用前のチェック体制が不十分なケースが見受けられ、企業にとっては重大な法的リスクにつながります。
カードの真贋判定に関しては、近年では精巧な偽造カードも出回っており、肉眼での判断が困難な場合もあります。このような背景から、ICチップ付き読み取り機の導入や、弁護士や専門家による事前確認、さらには入管への照会制度の活用が推奨されます。
採用実務においては、以下のようなプロセスの整備が効果的です。
雇用前確認の標準フロー(例)
- 在留カードとパスポートを原本で確認(コピー保存含む)
- 在留資格と職種の適合性をチェック(就労内容との照合)
- 弁護士や専門家に資格該当性を確認(不明点は必ず第三者に相談)
- 雇用契約書を適法な内容で作成(外国人専用のひな形を準備)
- 採用決定後、在留カードの管理・更新期限の記録
企業内に外国人雇用に対応する明文化されたマニュアルや社内規定が存在するかも、リスクマネジメントの上で重要です。特に中小企業においては、外国人雇用の経験が浅く、現場任せの採用判断となってしまっているケースも少なくありません。これにより、想定外の不法就労が発生するリスクが高まります。
定期的な在留資格の更新チェックや、雇用継続中の職務変更への注意も怠ってはならない点です。たとえば、当初は「通訳業務」で雇用したものの、業務の都合上「倉庫作業」に配置転換した場合、在留資格の範囲外となり不法就労に該当する可能性があります。
このように、在留カード確認とその後の運用は、単なる形式的な作業ではなく、企業の信頼性や法令順守を支える重要な工程です。外部の法律専門家と連携し、採用段階から定期チェック体制の確立、さらには在留情報のデジタル管理などを導入することが、これからの外国人雇用における競争力を左右するといっても過言ではありません。
外国人採用に必要な社内体制の構築方法
外国人を雇用する際、単に在留資格やスキルを確認するだけでは不十分です。企業が安定的かつ法令を順守しながら外国人雇用を継続するためには、採用から就労管理、社内コミュニケーションに至るまでを網羅した社内体制の構築が不可欠です。この体制が不十分であると、トラブル発生時の初動対応が遅れたり、不法就労やハラスメント、差別的扱いなどのリスクが高まり、企業の信頼性を大きく損なうことになりかねません。
外国人採用における社内整備で重要なポイントは、大きく以下のように分類されます。
外国人採用に必要な社内体制の主な構成要素
| 項目 | 内容 |
| 採用プロセスのマニュアル化 | 募集〜面接〜採用決定までの流れを標準化し、法令との整合性を保つ |
| 在留資格管理体制 | 在留カード・資格外活動許可・更新期限を社内でデータ管理する仕組みを整備 |
| 法務・労務部門との連携 | 就労範囲の確認、契約書の内容チェック、労務トラブル時の対応手順を明確化 |
| 多言語対応と相談窓口設置 | 英語・中国語などの対応資料整備と、外国人が相談しやすい環境を整備 |
| 社内教育と研修 | 採用担当者・現場管理者への外国人雇用に関する定期研修の実施 |
企業の成長とともに外国人労働者の比率が高まるなか、上記のような社内体制の整備は、経営上の必要条件とも言えます。特に在留資格の管理については、期限管理のミスがそのまま不法就労リスクにつながるため、紙ベースでの運用ではなく、クラウドシステムを導入した管理体制の確立が求められます。
外国人労働者の労働環境や就業条件に関するトラブルを未然に防ぐには、契約書の内容や説明責任の強化が必要です。日本語を十分に理解できない外国人に対しては、多言語での説明資料や逐語訳の導入が望まれます。採用時の誤解が原因で「聞いていた労働条件と違う」といったトラブルが発生し、企業と外国人労働者との信頼関係が破綻するケースもあるため、事前の認識合わせが極めて重要です。
コンプライアンス遵守の観点から、採用決定後には労務管理やメンタルケアの体制も整えておく必要があります。特に外国人労働者が孤立せず、安心して働ける環境を整えるためには、以下のような仕組みが効果的です。
外国人雇用におけるサポート体制例
- 専門知識を有する社内相談員の配置(法務・労務・生活支援等)
- LINEや社内SNSなどのツールを使った日常的なコミュニケーション体制の導入
- 生活に関するオリエンテーション(地域医療、住民票手続、銀行口座開設等)
- 外国人従業員からの意見を聞く定期面談・アンケートの実施
- 外部専門家(弁護士、行政書士、社会保険労務士)との顧問契約・相談体制の構築
特にコンプライアンス体制の構築においては、外国人労働者に特有の課題、たとえば「言語によるミスコミュニケーション」「文化的価値観の違い」「孤立によるメンタル不調」などに対応できる柔軟な制度設計が求められます。そのため、法務部門や人事部門だけでなく、経営層のコミットメントも重要です。
社内の各部門が連携し、外国人雇用に関するガイドラインを策定することで、現場での運用がスムーズになります。実際のトラブル事例や法改正に対応したケーススタディを元に、定期的なアップデートを行うことも、長期的な制度の維持と改善には欠かせません。
このような包括的かつ現実的な社内体制の整備が、外国人材の安定雇用と企業の持続的成長に直結する重要なカギとなります。これからの外国人採用は、制度理解と法令順守をベースとした「共生の仕組みづくり」こそが、他社との差別化となり、ひいては企業価値の向上へとつながるでしょう。
まとめ
外国人労働者の受け入れが進む今、日本企業には制度理解と法的対応の両立が求められています。特に在留資格の確認や契約書の整備といった実務面に加えて、差別的扱いや誤った労働管理によって、企業が法的リスクを負う可能性が高まっています。制度を正しく理解しないまま雇用を進めると、不法就労助長罪などの重大な問題に発展しかねません。
多様な文化背景を持つ外国人との雇用関係においては、母語に対応した契約書の作成や、在留資格に基づいた業務範囲の明確化など、きめ細やかな対応が不可欠です。解雇や雇止めを巡るトラブルでは、整理解雇四要件や通知義務といった法的ルールを軽視すると、訴訟や行政指導に発展するおそれもあるため注意が必要です。
そのようなリスクを未然に防ぐためには、法律事務所との連携や弁護士の関与が現実的かつ効果的な手段となります。特に労働問題に精通した弁護士は、契約書のチェックや在留資格の審査支援、解雇に関する法的アドバイスなど、企業に必要な支援を多角的に提供できます。
すでに外国人を雇用している企業も、これから採用を検討している企業も、今一度自社の体制や知識を見直し、必要な整備を行うことが重要です。適切な法的支援を受けることで、制度に準拠した雇用環境が実現し、長期的な信頼構築と人材定着にもつながります。安心して外国人と働く未来をつくるために、今こそ具体的な一歩を踏み出しましょう。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

| みなとワークス | |
|---|---|
| 住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
| 電話 | 052-387-9955 |
よくある質問
Q. 外国人雇用に弁護士を関与させるとどのようなメリットがありますか?
A. 外国人労働者を雇用する企業では、在留資格の確認や雇用契約の整備など複雑な法的対応が求められます。弁護士が関与することで、労働基準法違反や不法就労助長罪といった重大なリスクを回避できるだけでなく、行政機関との対応や書類作成を一括で支援してもらえる安心感があります。解雇通知の不備や差別的待遇に関するトラブルの未然防止にも効果を発揮し、企業の労務管理体制を根本から強化できます。
Q. 雇用前の在留カード確認にはどのようなチェックポイントがありますか?
A. 在留カードの確認は単に有効期限を見るだけでは不十分です。写真と本人情報の一致確認に加え、在留資格の種類が予定する業務に合っているかの精査、資格外活動許可の有無、履歴の記録管理が重要となります。偽造カードも年々精巧になっており、判断を誤れば企業側に不法就労助長の責任が生じるため、経験豊富な弁護士や法律事務所に確認業務を委託するケースも増えています。
Q. 技能実習制度や特定技能制度でのトラブルにはどんなものがありますか?
A. 技能実習制度では、受入れ企業が適切な支援計画を整備せず、実習生の労働環境に関する問題が多く報告されています。特定技能制度では、支援機関の不十分な対応や、日本語能力に起因するミスコミュニケーションが原因で業務トラブルが発生することがあります。こうした制度に関わる問題は、法律や行政手続きが複雑であり、弁護士が関与することで違反リスクの早期検知や外国人の権利保護につながります。
Q. 外国人労働者の解雇や雇止めを行う場合、何に注意すればよいですか?
A. 外国人だからといって、日本人と異なるルールで解雇することは許されません。整理解雇では四要件の充足が必須であり、雇止めの際も更新の合理的期待の有無を慎重に判断する必要があります。言語の違いや文化的背景からトラブルに発展しやすく、解雇通知の伝え方ひとつで労働問題や訴訟に発展するケースもあります。弁護士による交渉術や法的助言が、リスクの低減に直結します。
会社概要
会社名・・・みなとワークス
所在地・・・〒455-0068 愛知県名古屋市港区土古町2丁目5番地
電話番号・・・052-387-9955